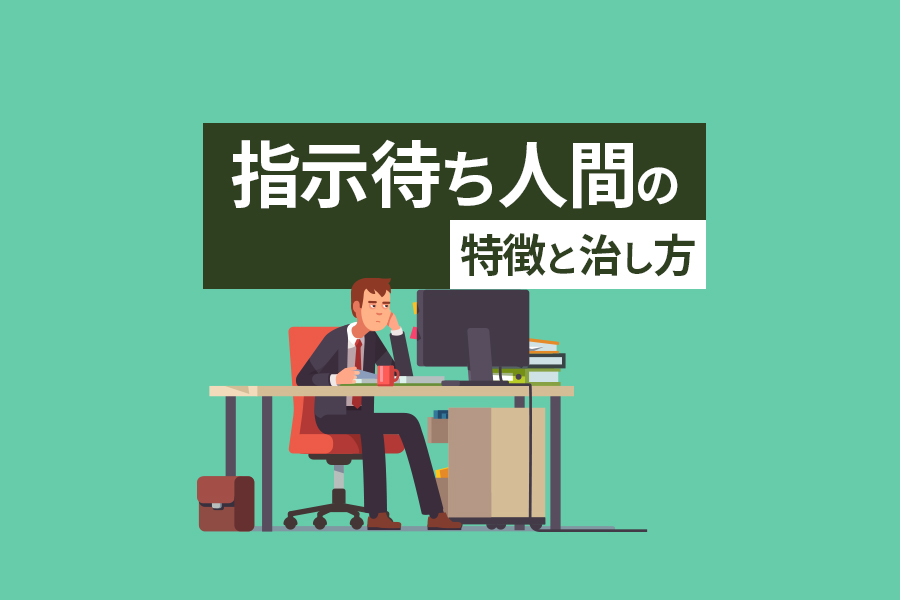

- いつも指示待ちになってしまう…
- 自分で考えて行動するのが苦手…
- 指示待ち人間は改善できるの?
そんなふうに悩んでいませんか?
指示がないと動けない「指示待ち人間」のままだと、評価が下がったり、チャンスを逃したり、働くこと自体がつらく感じる場合も。
本記事では、指示待ち人間の特徴や心理、原因を整理しながら、誰でも実践できる5つの改善策をご紹介します。
簡単なセルフチェックリストもあるので、自分の傾向を客観的に見直せます。
「自分を変えたい」「もっと前向きに働きたい」と考えている方や、部下育成に悩む人事・管理職の方にもおすすめです。
目次
指示待ち人間を改善したい方へ
私たちは起業やフリーランスに必要なスキルを無料で身につけられる、オープンイノベーション大学という学校を運営しています。
用意しているコンテンツは全て無料で学び放題。をしています。
どんなスキルが向いているのか診断もできますので、ぜひLINE登録(無料)して学習を始めてみてくださいね。
指示待ち人間とは何か?特徴と意味を解説
はじめに、「指示待ち人間」の定義を解説します。
主に仕事の場面で、次の行動を決められず立ち止まる、判断を人任せにするなど、受け身の姿勢が目立つのが特徴です。
ただ、誰でも環境や経験によって、指示待ち人間になってしまうことはあります。まずはその状態に気づき、自分を見直すことが改善の第一歩です。
指示待ち人間になる原因とは?
指示待ち人間になってしまう原因について解説します。
失敗したくない「防衛本能」
人は本能的に失敗を避けようとする傾向があり、これが「指示がないと動けない人」の行動の一因となっています。
特に日本の教育現場では、教師の指示に従うことが重視され、自ら考えて行動する経験が乏しいまま育つケースが多く見られるでしょう。
社会に出てからも上司の指示を待ち、責任を回避しようとする心理が働きます。失敗による評価の低下や人間関係の悪化を避けるための「防衛本能」ともいえます。
実際、リ・カレントの調査によると、若手社員の約40%が「失敗することに対して不安を感じている」と回答。
失敗を恐れるあまり、挑戦や創造的な行動が抑制され、結果として「指示待ち」の姿勢が強まってしまいます。
自己決定の経験不足
指示待ち人間になってしまう背景には、「自己決定の経験が少ない」が関係しているケースがあります。
幼少期から親や教師の指示に従って行動してきた場合、自発的に選んで動く経験が乏しくなりがちです。
その結果、社会に出てからも「どうすればいいかわからない」「自分で決めるのが不安」と感じやすくなり、自ら判断して行動する力が育ちにくくなります。
このような環境が続くと、指示がないと動けない状態に陥る可能性があります。
職場で意見を言えない雰囲気がある
指示待ち人間が生まれる背景には、「職場に意見を言いづらい空気」が影響していることがあります。
たとえば、上司や周囲の反応への不安や、過去に否定や無視された経験などがあると、再び意見を言うのを躊躇してしまうケースも。
「意見を言うと浮いてしまう」「波風を立てたくない」といった同調圧力が存在する職場では、部下が主体性を発揮しにくくなります。
指示待ち人間の特徴
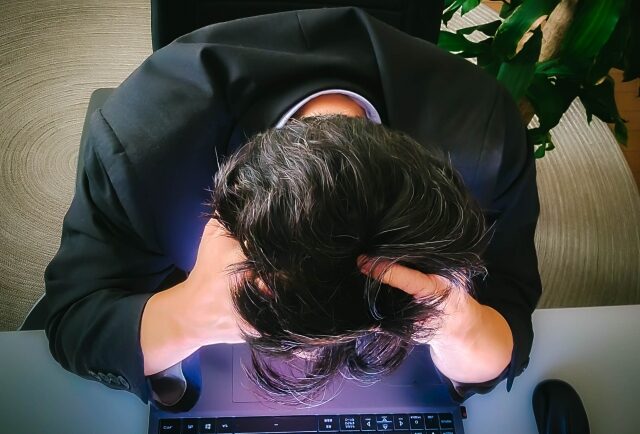
指示待ち人間の特徴について解説します。
判断・決断できない「優柔不断」
指示待ち人間の特徴のひとつは、「このまま進めていいのかな…」「確認したほうがいいかも」と迷ってばかりで手が止まる「優柔不断」の傾向です。
自分の判断に自信がなく、「正解が分からない」「失敗したらどうしよう」と不安になり、自発的に考えて動くことを避けがちです。
たとえば、メール1通送るのにも「この表現で合ってる?」「今送って大丈夫?」と、誰かに確認しないと動けないなど、指示がないと動けないのが特徴です。
自分の意見を出すのが怖い
指示待ち人間の特徴のひとつ、「自分の意見を出すのが怖い」と感じる背景には、過去の経験や心理的な要因が関係している場合が多いです。
たとえば、過去に意見を述べた際に否定された経験があると、再び同じような状況になることを恐れて発言を控えるようになります。
また、他人にどう思われるかを過度に気にするあまり、自分の考えを表現することに不安を感じる場合もあります。
仕事にやりがいを感じていない
指示待ちになりやすい人の多くは、仕事にやりがいを感じていません。
「頑張っても評価されない」「同じ作業ばかりで成長できない」「キャリアにも希望が持てない」などの不満を感じ、やる気が薄れている状態と言えるでしょう。
さらに、目標があいまいなままだと、達成感や前向きな気持ちも生まれにくくなります。
「どうせ何をしても変わらない」と思い込み、受け身のまま動けない人になる場合もあります。
コミュニケーションが苦手
指示待ちになりやすい人の中には、コミュニケーションが苦手な方も多く見られます。
「質問して怒られたらどうしよう」「余計なことを言ってしまうかも」といった不安から、報連相などの必要なコミュニケーションを避けてしまうのです。
その結果、わからないことをそのままにし、指示があるまで動けない状態になります。
自分の意見を伝えることに自信が持てず、会議やミーティングでも発言を控えてしまうため、周囲からは「主体性がない」と受け取られることもあります。
周囲への関心がない
指示待ちになりやすい人の中には、周囲の状況や人々に対する関心が薄い傾向があります。
たとえば、同僚が忙しそうにしていても、自分の業務が終われば手伝おうとせず、会議中に他のメンバーが困っていても気づかないといった行動が見られます。
結果として「言われたことだけをやる人」と評価されてしまう場合もあるでしょう。
周囲に無関心でいると、主体性や成長意欲を育てるチャンスを逃してしまうかもしれません。
あなたの指示待ち傾向は?〜チェックリスト〜

「自分って指示待ちタイプかも?」と感じたことはありませんか? まずは、今の自分の行動パターンを客観的にチェックしてみましょう。
以下の項目に何個当てはまるかを確認すると、指示待ち人間の特徴や原因への理解が深まります。
□ ミスが怖くて行動できない
□ 次の指示がないと動けない
□ 自分の意見を言わずに様子を見る
□ 何度も確認しないと不安
□ 周りの顔色を気にしてしまう
□ 楽な仕事から始める
□ 成果を「たまたま」と思っている
□ 他人の意見にすぐ合わせてしまう
□ 周囲の動きに無関心
□ 今の仕事にやりがいを感じていない
【結果の目安】
3〜6個:やや指示待ち傾向あり。行動パターンを見直すチャンス。
7個以上:指示待ち傾向が強め。小さなことから変化を起こしてみては。
いかがでしたか?あくまでも目安ですので、気軽に参考にしてみてくださいね。
指示待ち人間の何が悪い?デメリット3つ

指示待ち人間のデメリットを解説します。
業務の生産性が下がる
指示待ちの姿勢は、業務の生産性を大きく低下させ、タスクの進行が遅れがちになります。
また、上司や管理職は逐一指示を出さなければならず、マネジメントの負担も増えてしまいます。
このような状況が続くと、チーム全体の効率が落ち、成果にも悪影響を及ぼすでしょう。
さらに、主体的に動くメンバーとの間に不公平感が生まれると、周囲の不満やモチベーション低下を招くおそれもあります。
評価が下がりやすい
指示待ちの姿勢は、職場や企業での評価を下げる原因になります。
自ら考えて行動することが求められる職場では、受け身の態度が「積極性がない」「信頼しづらい」と見なされがちです。
結果的に、昇進や重要なプロジェクトへの参加の機会を逃すことにもつながります。
また、部下が指示待ちだと、上司のマネジメント力や管理能力が問われる可能性も。
さらに、指示待ちの姿勢は周囲のモチベーションにも影響を及ぼします。主体的に動く社員と評価が変わらなければ、周囲の不満やモチベーション低下につながることもあるでしょう。
組織全体のモチベーションが下がる
企業や職場に「指示がないと動けない」社員が多いと、「自分ばかりが頑張っている」と感じる人が出てきます。
積極的に動く社員がカバー役になり、業務の偏りが続くと、周囲に不満がたまりやすくなるでしょう。
また、誰も率先して行動しない雰囲気が定着すると、新入社員も「この職場では様子を見るのが正解」と感じ、受け身な姿勢が職場全体に広がっていきます。
結果として、全体の活気がなくなり、組織全体のパフォーマンスや士気が下がってしまうのです。
指示待ち人間を改善するメリット

指示待ち人間を改善するメリットをご紹介します。
キャリアの選択肢が広がる
指示待ちを改善すると、「この仕事、任せてみよう」と声がかかる場面が増えていきます。
たとえば、誰よりも早く気づいて資料を準備したり、会議の段取りを買って出たりするだけでも、周囲からの評価や信頼が大きく変わります。
日々の小さな行動が信頼を生み、やがて昇進や希望職への異動といったチャンスにつながっていくでしょう。
転職や副業でも役立つ「主体性」が身につく
指示待ちの姿勢を見直すことで身につく「主体性」は、転職や副業といった場面でも大きな強みになります。
たとえば面接では、「課題を自ら発見し、主体的に動いた経験」を具体的に語ることで、高い評価を得やすくなります。
また、副業ではスケジュール管理からタスクの遂行まで、すべてを自分で判断しながら進める力が不可欠です。
主体性のある人は、信頼を集めやすく、仕事の継続やキャリアアップにも直結します。
企業や業界が変わっても、汎用性の高いビジネススキルとして、今後も重要になるでしょう。
コミュニケーションが円滑になり仕事がしやすくなる
指示待ちの姿勢を見直すことで、職場のコミュニケーションは自然と活性化していきます。
たとえば、自分から進捗を報告したり、困っている同僚に声をかけたり、自発的な行動が増えていきます。
こうした積極的なやりとりの積み重ねは、チーム内の情報共有を促進し、結果として業務の効率化にもつながるでしょう。
さらに、日常的なコミュニケーションが増えることで、信頼関係が深まり、相談や意見交換もスムーズに行えるようになります。
指示待ち人間を治す方法5つ

指示待ち人間を治す方法をご紹介します。
仕事の全体像を理解する
仕事で「何をすればいいのかわからない」と感じるときは、まず全体の流れや目的を把握することが、自発的に行動するための第一歩になります。
目の前のタスクにばかり集中していると、全体像が見えなくなり、指示を待つ状態に陥りがちです。
そんなときは、上司やマネージャーの視点を意識することが有効です。
たとえば、チームリーダーの立場になって考えてみると、「チーム全体の成果を上げるには、今この仕事をどう進めるべきか?」といった視点が自然と身につきます。
こうした思考を重ねることで、目の前のタスクにも自分なりの判断軸が生まれ、主体的に行動できるようになるでしょう。
質問する癖をつける
指示がないと動けない状態から抜け出すには、わからないことをそのままにせず、自分から積極的に質問する習慣を身につけることが大切です。
たとえば、「この作業のゴールは何か?」「もっとよいやり方はないか?」といった問いを自分で立てることで、考える力が養われ、自然と主体性が育っていきます。
質問を通じて対話が生まれることで、職場のコミュニケーションも活発になります。
こうした日々のやりとりの積み重ねが、自発的に動くための確かな土台となるのです。
判断力・決断力を鍛える
指示待ちの姿勢の背景には、「判断力・決断力の不足」があることも少なくありません。
自分で考えて動けないと、「今動くべきか」と迷い続けてしまい、結果的に行動できない状態に陥ることもあります。
即断即決できる力があれば、自発的かつ主体的に行動できるようになり、受け身の姿勢を改善することができます。
判断力を養うためには、次のような習慣を日常に取り入れてみましょう。
- 日常の小さな選択に「時間制限」を設ける(例:1分以内に決める)
- 誰かに相談する前に、自分なりの答えを出す
- 軽い有酸素運動を日課にする(※)
(※)スウェーデン・ヨンショーピング大学の研究によると、2分〜1時間の有酸素運動は記憶力や判断力の向上に効果があるとされています。
こうした小さな実践の積み重ねは、自分自身の成長にとどまらず、部下やチームの主体性を育てる教育としても有効です。
コミュニケーションを大切にする
指示待ち人間から脱却するには、日頃からチーム内での円滑なコミュニケーションを意識するのが重要です。
HR総研によれば、企業の94%が社員間のコミュニケーション不足を「業務の障害」と感じています。
報告・連絡・相談(報連相)を習慣化すると、信頼関係が育ち、情報共有や意思決定もスムーズになります。
「この進め方でよいですか?」「こう考えたのですがどうでしょう?」と自ら声をかけるだけで、受け身の姿勢を脱し、自発的な行動へとつながっていきます。
自己効力感を高める
指示待ちの姿勢に陥りやすい人の多くは、「自分にはできない」と感じ、受け身になってしまう傾向があります。
一方で、自発的に行動できる人は、「自分ならできる」と信じて行動できる自己効力感が高いのが特徴です。
心理学者アルバート・バンデューラも、「自己効力感が高い人ほど成果を出しやすく、周囲からの信頼も得やすい」と述べています。
たとえば、「業務を効率化できた」「チームに貢献できた」といった成功体験を自分で認識し、前向きに評価する習慣を持つことで、自己効力感は高まりやすくなります。
完璧を目指すよりも、「まずやってみる」「動きながら考える」といった柔軟な姿勢が、自分自身の成長を後押しし、指示がないと動けない状態からの脱却につながるのです。
自分に合った仕事を知ろう

今の仕事に興味がなく、やる気が出ないために「指示待ち人間」になっている人は、適職について考えてみましょう。
乗らない仕事を続けていては、指示待ち人間を抜け出すのは難しいからです。
私たちは起業やフリーランスに必要なスキルを無料で身に付けられる、オープンイノベーション大学という学校を運営しています。
用意しているコンテンツは全て無料でLINE上で学び放題。あなたのペースで学習を進められます。
どんな職業が向いているのか診断もできますので、ぜひLINE登録(無料)して学習を始めてみてくださいね。
まとめ
今回は、指示待ち人間の特徴や原因、治し方について解説しました。
自発的に動けないことが悪いわけではありません。大切なのは、受け身の姿勢を少しずつ変えてみようとする意識です。
完璧を目指すのではなく、仕事に小さな楽しさや意味を見つけながら、主体性を育てていけば、長い目で見たときに自分自身の成長やキャリアの選択肢を広げることができます。
本記事が、あなた自身や部下・社員のマネジメントや教育に役立つヒントとなれば幸いです。
この記事は、起業家やフリーランスの新しい生き方を支援する「オープンイノベーション大学」が提供しています。
オープンイノベーション大学とは、Webデザインやプログラミング、動画制作など、フリーで働けるさまざまなスキルが学べる学校で、総計24万6千人の方が学んできました。
私たちの強みは、
- オンラインで自宅学習が可能(海外在住でもOK)
- 各業界の”現役で活躍する講師”から実践的なノウハウが学べる
- 専門スキル以外、マーケティングや集客スキルもしっかり学べる
- 横のつながりがあるので、仲間が増える
異業種・未経験で学習を始めた初心者の方が、学習後に現場で即戦力として活躍できる、スキルやノウハウが学べるカリキュラムに定評があります。
学習後に働けるのはもちろんのこと、学習段階で案件を受注して収入を上げる人も多数。
- 転職、独立のためのスキルが欲しい会社員の方
- 隙間時間で副業がしたい個人事業主、主婦、定年を迎えた方
といった、老若男女問わず、幅広い受講生の方々にご参加いただいています。

もしあなたが、
- 働き方や生き方を変えたい!
- 新たなスキルが欲しい!
- 収入の柱を増やしたい!
と思っていたら、ぜひLINE登録(無料)していただき、私たちが発信する情報をチェックしてみてください。
「何か行動したいけど、なにをすればいいのかわからない...」という方には、適性診断(無料)もご用意しています。
LINE登録後、3分程度で回答できる内容ですので、ぜひ試してみてくださいね。きっとこれまで知らなかった自分に気が付くヒントになると思います。
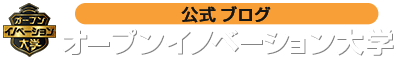




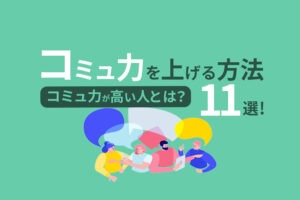
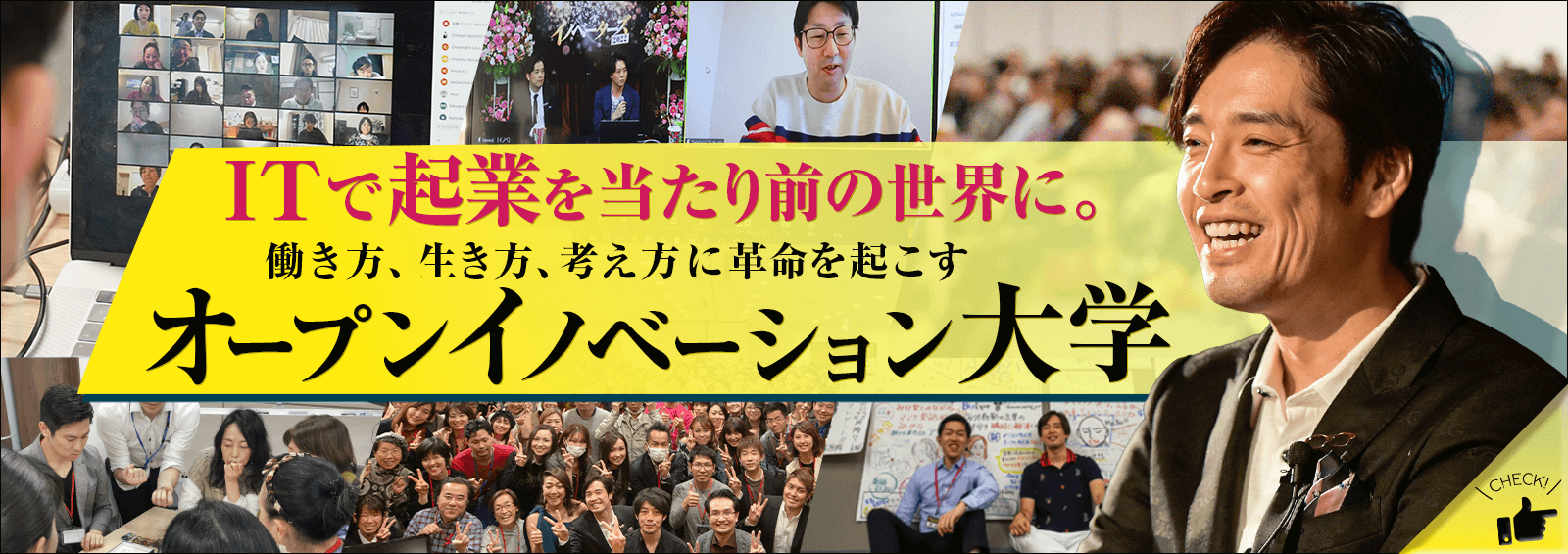

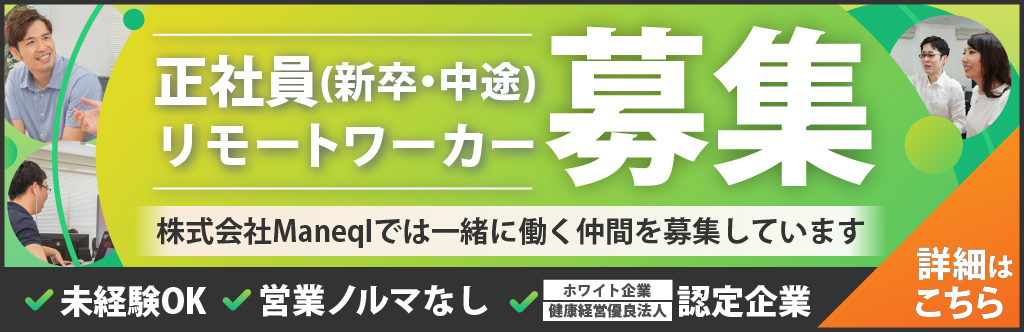
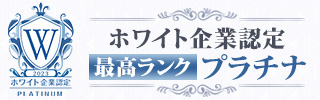

-1.jpeg)

